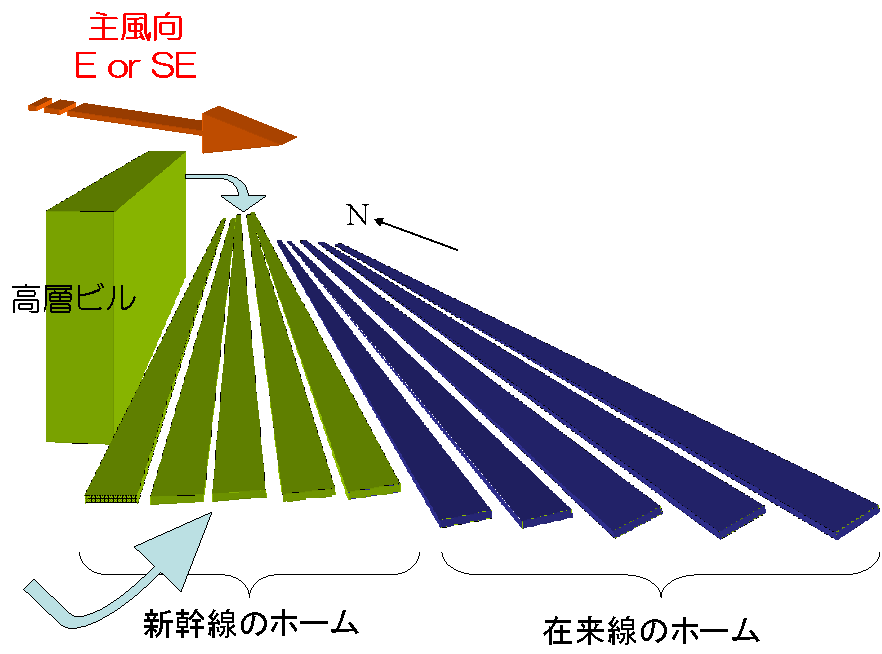ここでは,サーモグラフィの応用編の第2弾として,鉄道駅のホームに注目してみましょう.鉄道は私たちの生活に深くかかわっていますが,1日のうち電車の中と駅のホームにいる時間が2時間以上の人,必見ですよ!
下の絵を見てください.
駅の屋根には,真夏の昼間,さんさんと太陽光が降り注いでいます.このとき,屋根の表面温度は目玉焼きができるぐらいに高い温度になることは,「車の温度はどれくらい?」のところで勉強しましたね.
そうすると,屋根の表面で発熱した熱は,屋根の内部をつたわっていきます.そして,天井面の温度まで高くしてしまいます...ということは,天井から放射熱が出て,駅で電車を待っている人たちに降り注ぐことになりますね.
このように,建物の屋根や外壁,地面などが太陽光で発熱し,表面温度が上昇して放射熱を出すことを「再放射」といいます.
上で述べたように,鉄道駅の屋根に用いられている薄い鉄板やポリカーボネイト板でみられますが,そのほかには,例えばあなたの教室の窓のカーテンやブラインドでも,再放射の現象は起きています.
カーテンを閉めているのに窓際が暑い,と叫んでいるあなた!
暑い原因がわかりましたか?
これは,日本で一番大規模なターミナル駅のTK駅(もう,わかりますね)のホームを,夏の昼間にサーモグラフィでみたものです.上の段が在来線(東海道線)のホーム,下の段が新幹線(上越長野新幹線)のホームです.
在来線のホームでは,天井はポリカーボネイトとよばれる,薄い半透明の材料でできています.太陽光があたって45℃を超えていますね.
それだけではなくて,天井を突き抜けた太陽光が床や階段にも当たって,やはり40℃以上になっています.
さて,新幹線のホームですが,確かに階段の上にはポリカーボネイトの明かり取りがあって,表面温度は45℃ぐらいになっています.しかし,その左右両側は35℃ぐらいですね.
これは,新幹線ホームの屋根が,特に分厚く作られているからなのです.おおよそ1mぐらいの厚さがあります.ポリカーボネイトは階段の上などのごく一部にしか使われていません.
駅ホームの表面温度の特徴がわかりましたね.夏は,在来線の天井の方が,新幹線の天井のホームより高温になります.
では,在来線のホームに立ったときの方が,新幹線のホームに立ったときより暑いのでしょうか? 実は,これについては,緻密な調査データがあるのです.そんなお話を.
まず,T駅の風の流れを考えてみましょうか...
T駅では昼間,東京湾からの海風が吹いてきます.上の図のように東口の高層ビル(デパート)に風が当たります.すると,駅のホーム上には,北からと南からの風が巻き込んでくることになります...すると,各ホームのちょうど真ん中では,北からと南からの風がぶつかって,風が弱くなります.
さて,ホーム上では電車がクーラーを運転したまま停車しています.どんどん熱を車外に逃がしているわけなのですが,この熱は,列車の停車時間が長いほどたくさん駅構内にたまりますね.さらに,風が弱いところであれば,吹き飛んでいくことがなく,結局気温が上昇することになります・・・つまり,新幹線のホームでは,比較的停車時間も長くて,また高層ビルのすぐ裏で風も弱いため,気温が上昇しやすいのです.
このことを裏付けるデータがあります.
これは,3時間ごとに,ホームの真ん中の気温を比較して,折れ線でつないだものです.
早朝は1.5℃,昼間は1.2℃,そして夜間は2.0℃も新幹線のホームの方が気温が高いんです...表面温度のときとは,逆の関係にありますね.
ちなみに,人間の体感にとって,取り囲む周りのものの表面温度が全部1℃上昇して再放射をうけるということは,気温が1℃上昇することと同じぐらいの温度上昇の感覚だそうです.
・・・「夏,道路に水をまく」ということの意味が,少しだけ見えてきましたね・・・